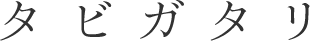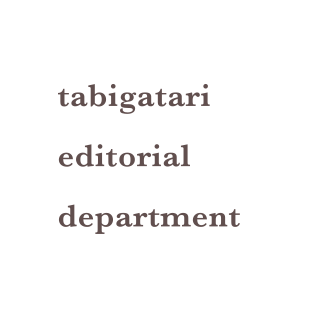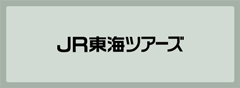京都における“リフレクション写真”の火付け役的存在。
SNSをきっかけに、大人気スポットへと変貌を遂げることがある。市街地から大原へと抜ける途中、普段はひっそりとした八瀬の地に佇む〈瑠璃光院(るりこういん)〉もそのひとつだ。机に映り込むモミジの絶景が話題となり、京都を代表する寺院となった。春季、夏季、秋季に期間限定で公開されるが、最も大勢の人出で賑わうのは紅葉の秋。今年こそはぜひ行きたいとお考えの方も多いことだろう。秋に訪ねた模様をお届けしよう。
※本記事の写真は2024年以前に撮影したものも含みます。
紅葉が見頃となる時季に瑠璃光院を拝観するのであれば、一部期間を除いて、希望する拝観日時を指定した「事前抽選予約」への申込みがマスト。公式ホームページから申込みをして当選となれば、当日、指定の拝観時間を目指して現地へ向かうことになる。〈瑠璃光院〉への最寄り駅となるのは、叡山電鉄の「八瀬比叡山口駅」。「京都駅」からJR奈良線に乗って「東福寺駅」まで向かい、京阪電車本線に乗換えて「出町柳駅」へ。そこから叡山電車本線に乗換えれば到着だ。2度の乗換えは億劫に感じるが、秋の京都旅では交通渋滞が悩みの種。渋滞に巻き込まれることがなく、時間が「読みやすい」電車は、旅の心強い味方となるのだ。〈瑠璃光院〉の拝観には「時間指定」があるので、なおさらに電車利用がおすすめだ。
静寂な庭のある名刹と森深い古社を散策。
「八瀬比叡山口駅」から瑠璃光院までは、歩いて13分ほど。まっすぐ向かうのも良いが、周辺観光も予定に組み込んでみることにした。「八瀬比叡山口駅」の一つ手前の「三宅八幡駅」で下車して、歩いて8分ほどの〈蓮華寺〉へ。
書院前の庭
本堂
いよいよ〈瑠璃光院〉の“絶景”へ。
〈祟道神社〉から国道を東に12分ほど歩き、高野川に架かる「雰囲気のある橋」を渡ると「ケーブル八瀬駅」へ。そこから、川と並行する道を下流方向に7、8分歩けば、いよいよ〈瑠璃光院〉が見えてくる。山門脇の受付で拝観の手続きを済ませ境内へと進む。霊峰比叡山の山麓に位置することもあってか、玄関手前に広がる「山露地(やまろじ)の庭」は、霊気が漂うかのようで、エネルギーに満ちあふれてくる心地さえする。空を覆うモミジと青々しい苔が美しく、まずはここで息を整えよう。
山露地の庭
「喜鶴亭」の文字は三条実美による揮毫
かま風呂を後にして院内を進むと、「机の部屋」のちょうど真下へ。紅葉と主役争いをするかのような美しい苔に目が奪われる。それぞれの彩りだけでなく、苔とモミジのコントラストもじっくりと目に焼き付けたい。
瑠璃の庭
〈瑠璃光院〉のライトアップが見られるのは、JR東海の「秋の特別拝観」のみ!
JR東海では、例年春と秋に「特別拝観」を実施し、「プラン限定開催のライトアップ」が目玉の一つとなっている。要するに、一般向けには開催されておらず、特定のプランを購入した人のみが参加できる夜間拝観のことだ。〈瑠璃光院〉でのライトアップは、やや高価格ではあるものの、人数限定で幻想的な紅葉風景を楽しめるため、毎年好評であるという。今年で9年目の開催ということからも、その人気ぶりが窺える。〈瑠璃光院〉までのアクセスに便利な、「叡山電車1日乗車券」や「叡山ケーブル・ロープウェイ往復乗車券」もセットになっているので、沿線の名所めぐりと一緒に楽しんでみては?
瑠璃光院
Text & Photo:Kazuaki Toda
いつもと違う京都府観光には、〈瑠璃光院〉がおすすめ。
瑠璃光院
| 所在地 | 京都市左京区上高野東山55(Google Map) |
| アクセス | 叡山電鉄叡山本線「八瀬比叡山口駅」から徒歩約13分 京都バス「八瀬駅前」バス停から徒歩約7分 |
| URL | https://rurikoin.komyoji.com/ |
| 拝観時間 | 10:00~17:00 ※秋の特別拝観は2025年10月1日(水)~12月14日(日) ※2025年11月8日(土)~12月7日(日)の拝観は、事前予約抽選制となります。予約方法などは公式ホームページよりご確認ください |
| 拝観料 | 2,000円 |
蓮華寺
| 所在地 | 京都市左京区上高野八幡町1(Google Map) |
| アクセス | 京都バス「上橋」バス停からすぐ 叡山電鉄叡山本線「三宅八幡駅」から徒歩約7分 |
| 電話番号 | 075-781-3494 |
| 拝観時間 | 9:00〜17:00 |
| 拝観料 | 500円 |
祟道神社
| 所在地 | 京都市左京区上高野西明寺山町34(Google Map) |
| アクセス | 叡山電鉄叡山本線「三宅八幡」駅から徒歩約8分 京都バス「上橋」バス停から徒歩約2分 |
| 電話番号 | 075-722-1486 |
| 拝観時間 | 境内自由 |
| 拝観料 | 無料 |
※記事中の商品・サービスに関する情報などは、記事掲載当時のものになります。詳しくは店舗・施設までお問い合わせください。