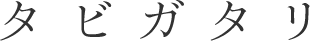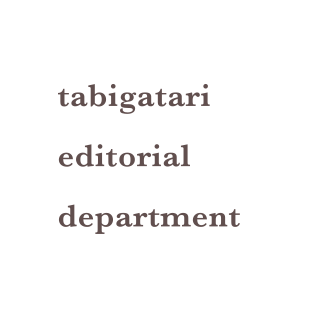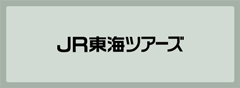大事にしているお気に入りの器が割れてしまったとき、美しく蘇らせる方法として「金継ぎ(きんつぎ)」と呼ばれる技法がある。“物を大切にする心”から生まれた日本の伝統技法であり、現在も全国各地で金継ぎの体験ができる。今回は古き良き文化を体感するため、京都で金継ぎ体験と一緒に、精進料理教室にも参加してみよう。旅を通して、長い年月をかけて磨かれた日本の伝統に触れていきたい。
〈東林院〉で精進料理を作り、味わってみる。
最初に訪れたのは、花園駅から歩いて10分ほどの位置にある〈東林院〉。妙心寺の塔頭(たっちゅう)のひとつである〈東林院〉は、毎年6月に美しい沙羅の花が咲き誇ることから、沙羅双樹の寺とも呼ばれている。
ここでは週に2回ほど精進料理の体験教室を開催している(要予約)。教えてくれるのは、精進料理について数々の著書をもつ西川玄房住職。自身が好きな料理を通して、生き物の大切さや“不殺生戒”の教えを伝えたいと思い、1999年に精進料理教室を始めた。作ること、食べることの意味を禅の修行に絡めて話しながら、目の前の命をいただくありがたみを伝える。
家庭でも取り入れやすい精進料理を学ぶことができると人気で、リピーターや遠方からの参加者も多いこちらの料理教室。調理は〈東林院〉の厨房である「添菜寮(てんさいりょう)」で行う。今日の献立は「揚げうどんのカブラ蒸し」、「カレー豆腐のあんかけ」、「春菊とマイタケのゴマ酢和え」の3品。旬の食材を使った料理や、冬ならではの体が温まる料理が選定された。まずはお茶をいただきながら、西川住職より3品の作り方や精進料理の心得などを聞く。
この体験で「生かす心に目覚めてほしい」と西川住職は話す。精進料理は肉や魚を使わないだけでなく、食材を無駄にせず活かし切る心が大事だという。
「野菜や果物などの植物にも命があり、人間は生きている限り、これらの命をいただかなければなりません。食材の命を思いやって残さずいただき、自分の命につなげることが大事です。また、電気や水道にもたくさんの命が犠牲になっていることを忘れてはいけません」と西川住職。
たとえばガス管や水道管を埋める工事によって木々が伐採されたり、土壌の微生物に影響が出たりなど、私たちの生活はさまざまな命のうえに成り立っている。だからこそ、電気やガスを無駄にせず、上手に活かしきることが必要だ。
調理は3〜4人がひとつの班となり、協力して行う。先ほどの西川住職の教えをもとに各自で考えながら作業を進めるのが、この料理教室の特徴。野菜の皮や根を捨てずに使う、煮汁を活用するなど、食材を無駄にしないための方法を考え実行していく。洗い物をなるべく増やさないなど、水を無駄遣いしない意識も大事だ。
調理時間は全部で約70分ほど。温かい料理はなるべく出来立てを食べられるよう、逆算して調理の順番を考えることもポイントのひとつ。
3品の料理が完成したら、各自で盛り付け・配膳まで行う。参加者が作った3品以外に、西川住職が作った品が加わって、立派なお膳に。
参加者みんなが揃ったところで、枯山水のお庭が見える部屋にて自分たちが作った精進料理をいただく。心をこめて作った料理は、じんわりと体に染みわたるようなおいしさだ。
最後に西川住職は、自分が住む土地のものを食べる素晴らしさを教えてくれた。
「同じ空気や水、土で育った七里四方(約30km四方)の食材は自分の体に良い、と古くから言い伝えられています。その土地の食材、そして旬のものを食べることは、日本の気候風土を活かすこと。普段から意識することで、たまに季節外れの食材や地方のものを食べたときに、本当の意味で贅沢を感じられます」
精進料理を作り食べる体験で、自然の恵みとしての食材や生産者、調理する人へ感謝の気持ちを決して忘れてはいけないことを学んだ。
金継ぎを体験しに〈POJ Studio〉へ。
京都駅に戻り、金継ぎを体験しに〈POJ Studio〉へ向かう。〈POJ Studio〉は日本の伝統工芸業界の課題解決に貢献するため、米シリコンバレーのIT業界で活躍していた小山ティナさんが、ニューヨークでアートディレクターをしていた塚本はなさんと一緒に立ち上げたライフスタイルブランド。産業の衰退や人材不足などの問題を抱える伝統工芸業界を盛り上げ、その魅力を広めたいという思いから、2020年より海外向けに美しい工芸品やオリジナル商品を扱うオンラインショップを始めた。
2022年には、本物の伝統工芸品を現地の日本で体験できるよう、京都の古き良き街並みが残る東山エリアに実店舗をオープン。1階は販売スペース、2階は体験教室の工房という造りになっており、より伝統工芸品を身近に感じてもらえるお店を目指した。築100年の京町屋を改装して造られたお店は落ち着いた雰囲気で居心地が良く、国内外から多くのユーザーが訪れる。
〈POJ Studio〉では特に金継ぎの体験に力を入れている。金継ぎとは、漆を使って欠けやひび、割れが生じてしまった器を修復する技術。仕上げに金粉などを使って装飾を行えば、修復した箇所を活かしながら器に新しい価値を与えることができる。
さらに、日本国内で急速に縮小しつつある漆産業を支援するため、体験教室以外に、器の修理の受け付けやユーザーが自宅で器を修復できるキットの販売など、金継ぎに関する取り組みを幅広く行う。金継ぎが身近になり利用者が増えれば、今ある器を修復しながら大事に使う意識が芽生え、ゆくゆくは不要なカーボンフットプリントの削減につながると考えている。
金継ぎは大まかに「割れた器をくっつける」「欠けた箇所を埋める」「表面を滑らかに整える」「金属粉を蒔く」という流れで行われる。いずれの工程にも漆が使われており、作業ごとに硬化させるための時間が必要となるため、ひとつの器を直すには約2ヶ月ほどかかる。温度25〜30度、湿度65〜80%に整えた「室(むろ)」で保管し、漆の性質を利用しながら硬化させていく。
京都には漆の代わりにエポキシパテなどの合成樹脂を使って接着する簡易金継ぎの店舗もあるが、〈POJ Studio〉では本格金継ぎの体験が可能だ。さまざまなコースがあるなかでも今回は、金継ぎの工程で最初のステップとなる器のかけらをくっつけるコースを体験した。
コースの体験時間は全部で2時間ほど。金継ぎそのものや作業の流れについて説明があった後、器の割れた断面を整え、「麦漆(むぎうるし)」で接着する作業まで行う。こちらの体験では、これから直す器に向き合うため、特別に割れた器のスケッチからスタート。どこにどんな割れや欠けがあるか器を全方向から観察し、ノートにスケッチして専用のカルテを作っていく。
「初めて金継ぎにチャレンジする方の場合、作業をしていくうちに細かい欠けやヒビがわからなくなってしまうことがあるので、最初に器を診断することが大事です」と教えてくれたのは、金継ぎ講師の内藤さとこさん。
体験コースで使う器は、2つに割れたコース専用の磁器。初心者には釉薬(ゆうやく)がかかった磁器がもっとも作業しやすいそう。
「陶器や釉薬なしの器は漆が浸透しやすいので、継ぎ目の周囲などにシミができる可能性が高くなります。また、慣れていない方にとっては、複数に割れた器をきれいにくっつけるのは少し難しいです。まずは作業しやすい器で体験してから、お気に入りの器の金継ぎにチャレンジすることをおすすめします」
割れ具合や器の特徴を見極めたら、さっそく作業へ。漆がしっかり定着するよう割れた欠片の断面をダイヤモンドヤスリで削り、細かい溝をつけていく。この作業を行うことで、次に塗る希釈漆が器の中に染み込みやすくなるそう。
続いて生漆(きうるし)をテレピン油で希釈したものを、欠片の断面、ヒビ、かけている部分に塗っていく。漆は肌につくとかぶれてしまう恐れがあるため、ここからの作業は手袋が必須。内側から外側の順番で作業すると、余計なとこに漆がつきにくくキレイに塗れる。
次に器を接着するための「麦漆」を作る。小麦粉を使うので「麦漆」と呼ぶのだそう。最初に小麦粉と水をあわせてこね、そのあとに生漆と混ぜ合わせる。
「小麦粉のグルテンを活かしたいので、8の字をかくイメージでこねて粘り気を出していきます。目指すはピザ生地くらいの粘度。同量の生漆と混ぜ合わせたら、麦漆の完成です」
余分な希釈漆をティッシュで拭き取った後、竹のヘラを使って割れの断面に麦漆をのせていく。パンにバターを塗る感覚で、薄く均等にのせるのがポイントだ。まんべんなく麦漆が塗れたら、いよいよ割れた欠片同士をくっつける作業へ。
「この段階では麦漆が柔らかいので、動かしながらぴったりフィットするところを探ります。欠片同士をギュッと押し合わせたり、すり合わせたりしてみてください」
ぴったりくっついたら作業は完了。外れないようにマスキングテープで固定して、1週間を目安に〈POJ Studio〉の室で保管後、できあがった器は自宅へ郵送される。そのままの状態で記念にオブジェとして飾る人もいれば、金継ぎキットを購入して続きの作業を自宅で行う人もいるそう。
「完全に修復するまで月日はかかりますが、器と向き合う時間は瞑想のような詩的なひとときでとても心地良いんです。手をかけるからこそより器に対する愛着が湧くと思います」と金継ぎの魅力を語ってくれた内藤さん。
2時間の体験で、昔から物を大事にする日本人の心を学ぶことができた気がした。
京都での精進料理教室と金継ぎ体験で、食材や物を無駄にしないことの意味や大切さを改めて考えさせられた。日本のこういった伝統には、サステナブルな精神が息づいている。さらに京都の町を歩くと、量り売りの小さなお店が点在していたり、公共交通機関が発達していたり、EVバスが走っていたりなど、サステナブルな暮らしにつながるヒントがたくさんあることに気づく。持続可能な未来のために、個人でできることはたくさんある。今回の旅をきっかけに自分の生活を見直し、未来へとつなげていきたい。
Text:Ayumi Otaki
Photo:Misa Nakagakiいつもと違う京都府観光には、京都市の〈東林院〉〈POJ Studio〉がおすすめ。
東林院 精進料理体験教室
| 所在地 | 京都府京都市右京区花園妙心寺町59 |
| アクセス | JR「花園駅」から徒歩約8分 |
| 電話番号 | 075-463-1334 |
| 営業日時 | 毎週火曜、金曜 ※除外日あり
10:00〜13:00 |
| 料金 | 3,600円(材料費・テキスト代含む)
※要予約(電話にて問い合わせ後、往復はがきで申込み) |
POJ Studio
※記事中の商品・サービスに関する情報などは、記事掲載当時のものになります。詳しくは店舗・施設までお問い合わせください。