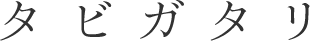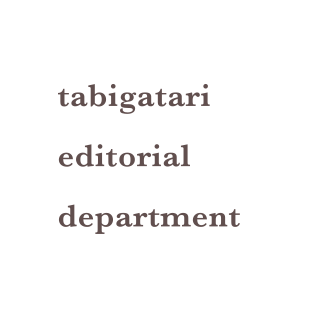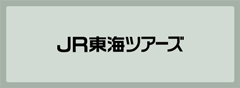「好き」から始めた、山の読書室
富士山の西麓、朝霧高原に位置する富士宮市。キャンプ場や源頼朝にゆかりのある「陣馬の滝」など、豊かな自然に恵まれた猪之頭地区に、築60年以上の納屋を改装した〈虹ブックス〉がある。店主の古屋淳二さんが夫婦で営む読書室だ。自身の出版社〈虹霓社(コウゲイシャ)〉から1文字とり、本屋ではないが本がある場所だとわかるように〈虹ブックス〉と名付けた。
古屋さんは就職を機に上京して、しばらく東京で働いていた。結婚して子どもが生まれてから、東京を離れることを考え、地域おこし協力隊として徳島県に移住した。3年ほど過ごして、知り合いの紹介で富士宮にやってきた。「母屋と納屋と畑があって、何かできそうだと思いました。観光スポットに近くて、富士山もよく見えて、家の前に湧き水も出ている。環境のよさもここを借りる決め手になりました」。古屋さんは振り返る。最初はコワーキングスペースをつくろうと始めてみたが、計画は変わった。「週末に多くの人がキャンプに来る地域なので、需要があると思ったんです。でも自分たちが興味を持てなかった(笑)。2人とも本が好きだし、蔵書もたくさんあったので、図書室にしようと」。オープン時に知り合いの映像作家が本を寄贈してくれたり、オープン後は地域の人が漫画を寄贈してくたり、自身が好きな本を購入したり。増え続ける蔵書は、もともと納屋にあったものをリメイクしてつくった棚などに収められている。
「おもしろいもの」に出会える場をつくっていきたい
〈虹ブックス〉の営業は、週3日。営利活動ではなく、文化運動だと古屋さんは言う。「本っておもしろいじゃないですか。こういうおもしろい本があるよと伝えたいし、知ってほしい。どちらかというと公立図書館や一般的な本屋さんでは見かけない本をそろえていて、そういう本と出会える場、違う世界を知るきっかけの場にしたかったんです」。蔵書は、アート、思想、文学、サブカル、漫画などさまざま。中でも農的生活や移住など田舎暮らしに関する本が最近は人気だという。
「偏りがある」という蔵書の中から選んでくれたのは、つげ義春さんの紀行エッセイ集「貧困旅行記」。「つげ義春という作家の魅力のひとつに、存在の危うさみたいなところがあると思うんです。どこか俗世間からの逃避願望を抱えたような旅で、秘境めいた、あまり人が行かない場所に行くんです。その描写がとてもおもしろい。変な旅館に行ったエピソード、親子の旅のエピソードが好きです。1990年代の作品なので、今は存在しない場所もあると思います。だから今読むとリアルとフィクションが混ざり合った感じがして味わい深いです。地図も書いてあるので、行こうと思えば行けちゃいます。旅に出る前にはぴったりですね」。
古屋さんは〈虹霓社〉と〈虹ブックス〉を運営するほか、町おこしのNPO団体にも参加している。いろいろな肩書きがあるため「結局、何をやっている人なの?」と聞かれることも多いそうだ。出版社や編集の仕事も読書室もNPOも、根っこは同じだと古屋さんは言う。「世にあるおもしろいものを、広く知ってほしい。その伝え方の違いですかね。最近〈虹ブックス〉でコーヒーを提供しているので、近所の人にはコーヒー屋さんと思われているかもしれませんけど(笑)」。伝えるものが変われば、伝え方も変わるものだ。
地方出身者が地元の話をすると、「田舎だね」という反応と「いいところだね」という反応に分かれることがある。その違いは、地域が魅力的に映るかどうかだ。「おもしろいものがある場所には、自然と人が集まってくるじゃないですか。ここでも読書会を始めて、ちょっとした集まりを定期的に開いていこうと考えています。その中の誰かが『ウチの地元には、こんなにおもしろいものがある』と誇らしく思える場所になれたら、とてもうれしいですね」。
Text:Atsushi Tanaka
Photo:Shinya Tsukiokaいつもと違う静岡県観光には、富士宮市の〈山の読書室 虹ブックス〉がおすすめ。
山の読書室 虹ブックス
※記事中の商品・サービスに関する情報などは、記事掲載当時のものになります。詳しくは店舗・施設までお問い合わせください。